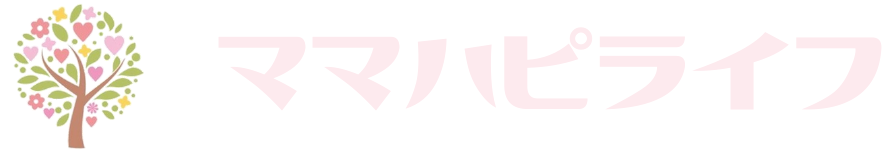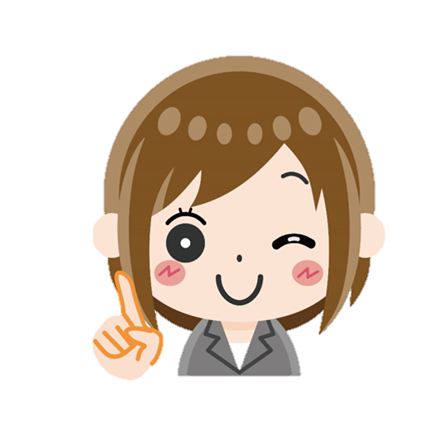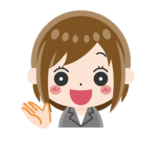妊娠して嬉しい!という気持ちの一方でこれから約10ヶ月の間、どれくらいの頻度で健診があるんだろう?
健診って痛いの?何をやるの?と不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回はそんな方のために、妊婦健診のスケジュールと具体的にいつ・どんな事をやるのか?
について分かりやすくお伝えしたいと思います。
それでは早速見てみましょう!
妊婦健診のスケジュールは?何回産婦人科に行くの?

実は、妊婦健診のスケジュールの目安頻度は厚生労働省より下記のように定められています。(※1)
・妊娠初期~23週: 4週間に1回
・妊娠24週~35週: 2週間に1回
・妊娠36週~出産まで:1週間に1回
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken13/
40週0日が予定日とされいますので、予定日ちょうどに生まれたとしたら、
妊婦健診は妊娠中、約14回受ける事になります。
「妊婦は病気じゃないのになぜ健診を受けるのだろう?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
妊婦はたしかに病気ではありませんが、妊娠期間中は母体が急激に変化をする時期でもあります。
食べられないモノや、してはいけない事、気をつけなければいけない事も各段に増えます。
「マタニティーブルー」といって、普段は何ともない事も異常に不安に感じてしまったり精神的に不安定になることも。
また、「順調」と思っていても、いつ、切迫流産などのトラブルに見舞われるかは分かりません。
心身共に健康に過ごし、母子ともに無事に出産を迎えるために、妊婦健診は必須なのです。
各時期で必須の検査はあるの?検査内容はどんなもの?

各時期において受けた方が良い・受ける事を推奨されているのは下記のような検査です。
細かい内容等については、各自治体や病院によって方針が異なる事もあります。
妊娠初期~23週に受ける検査
・血液検査(血液型・血算・血糖・B型肝炎抗原・C型肝炎抗体・HIV抗体・梅毒血清検査・風疹ウィルス抗体・HTLV-1抗体)・子宮がん検診・超音波検査・性器クラミジア
妊娠24週~35週に受ける検査
・血液検査(血算・血糖)・B群溶血性レンサ球菌・超音波検査
妊娠36週~出産の間に受ける検査
・血液検査(血算)・超音波検査
・NST(ノンストレステスト):おなかにセンサーをつけて、30~40分ほど安静にして行う検査のこと。
母体の子宮収縮の状態ならびに赤ちゃんの心拍を調べ、赤ちゃんが分娩のストレスに耐える事が出来るかどうか?を確かめる検査。
全期間を通じて受診する検査
全期間を通じて、「健康状態の把握」「検査測定(子宮底長、腹囲・血圧・浮腫・尿蛋白・糖尿・体重)」「保健指導」は実施されます。
このタイミングを通じて、不安な事を先生に相談したり、検査で異常な値が出た場合は、栄養士なども交えながら解決策を考えたり、場合によっては入院をする事もあります。
内診を受診される際のポイント
「内診」が苦手な方もいらっしゃるかと思いますが、緊張すると、至急に力が加わり、内診が余計に痛く感じる事も。お産の練習だと思い、ゆっくり・長く息を「吐く」事を意識して診察を受けましょう。
採血が苦手な方
「採血」が苦手、と言う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
こちらも、緊張をすると血管が収縮してより時間がかかってしまいます。
カイロや自分の手を使って身体特に採血部分の血管を温めると、血管が浮き出てきて採血がスムーズに進みますよ。
受診結果や相談がなかなか聞けない方は…
先生が忙しそうでなかなか聞きたい事が聞けない…という場合は
あらかじめ質問を2個程度に絞って考えておくのもオススメです。
産婦人科には複数の先生がいらっしゃる事もあるかと思いますが、「この人が良い」というお気に入りの先生を見つけたら、指名できたりする病院もあるようです。
その方が担当の曜日もあるかと思うので、担当の曜日に予約を入れる事を意識してもいいですね。
妊婦健康検査補助券とは?
各自治体から母子手帳交付の際に「妊婦健康検査補助券」なるものが渡される事がほとんどかと思います。
これを提出する事によって、妊婦健診の費用を補助してもらえるという優れモノです。
内容・補助額は各地域まちまちですが、里帰り等をした場合も、所定の手続きをすれば、後日、補助金額がかえって来る事も多いですので、補助券を支給された際に一度確認をしてみる事をオススメします。
妊婦健診のスケジュール・頻度・検査一覧まとめ
以上、妊婦健診のスケジュール・頻度と、各時期に実施する検査についてまとめました。
10ヶ月という期間は長いようであっと言う間です。
定期的に妊婦健診を受ける事で、お腹の赤ちゃんの成長も感じられ、母性が育まれるとも言われています。
妊婦健診を積極的に利用しながら、無事、元気な赤ちゃんを出産下さいね♪